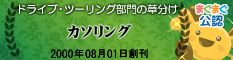東北四端紀行[29]
投稿日:2017年3月22日
北端編 9 龍飛は本州の袋小路だった
三厩を出発し、スズキDR−Z400Sを走らせ、国道339号で津軽半島最北端の龍飛崎に向かう。龍飛崎までの間には点々と漁村がつづく。龍飛に到着。龍飛漁港の行止り地点には、太宰治の『津軽』の文学碑が建っている。それには次のよな一節が彫り刻まれている。
ここからは高台上の龍飛崎へと、国道339号の日本で唯一の階段国道が通じている。ぼくが「30代編・日本一周」で龍飛崎にやってきたのは1978年のこと。そのときは太宰治の『津軽』どおりの世界で、ここが行止りだった。国道339号で日本海側の小泊に抜けられるようになったのは、まだ最近のことなのである。
龍飛漁港から自動車道で龍飛崎の台地上に登っていく。龍飛崎は高さ100メートルほどの断崖となって落ちている。断崖の下に龍飛の集落があり、龍飛漁港がある。漁港の前の帯島が天然の防波堤の役目を果たしている。龍飛はまさに帯島のおかげといってもいい。もしこの小さな岩山がなかったら、きっと無人の荒野だったことだろう。
龍飛崎では龍飛崎温泉「ホテル竜飛」(入浴料500円)の湯に入った。大浴場の湯につかりながら津軽海峡を眺め、対岸の北海道最南端の白神岬を眺めた。「絶景湯」だ。龍飛崎から白神岬までは19キロでしかない。
龍飛崎温泉の湯から上がると、「津軽海峡冬景色」の歌謡碑前でDRを停めた。
北のはずれと
見知らぬ人が 指をさす…
そんな歌詞の彫り刻まれれた歌謡碑の赤いボタンを押すと、石川さゆりの歌声が聞こえてくる。
つづいて国道339号の「階段国道」を登り下りした。いや、正確にいうと岬上から下り、また登った。そして龍飛崎の突端へ。土産物店の並ぶ駐車場にDRを停め、白い灯台前から岬の要塞跡へ。龍飛崎は昔も今も北方警備の要衝の地。
弘前藩は文化5年(1808年)、この地に台場を築き、狼煙台と砲台を設置した。明治以降は旧日本海軍の監視所になった。現在もここには海上自衛隊のレーダー基地がある。龍飛崎は「風の岬」で知られているが、周辺の丘陵地帯には何基もの風力発電の風車が見られた。

 三厩を出発
三厩を出発