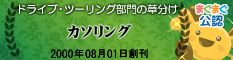第11回 観文研の思い出
投稿日:2010年12月27日
2010年 林道日本一周・西日本編
日本をめぐることで新たな世界が開けた
紀伊半島の玄関口、五條では国道24号沿いの「リバーサイドホテル」に泊まった。宿泊者は隣接している「金剛の湯」に無料で入れる。ここは大深度温泉で地下1300メートルから温泉をくみ上げている。
槇の大風呂、露天の岩風呂につかりながら、
「フーッ!」
と、大きく息をつく。
ゆったり、まったりできる、たまらんひと時だ。
龍谷大学の須藤護教授に会ったこともあって、湯につかっていると、無性になつかしく日本観光文化研究所(観文研)が思い出されてくるのだった。
観文研が解散してからすでに20年以上もたっているが、1年たつごとに、そのなつかしい気持ちは自分の心の中で増している。
観文研末期の頃はおどろおどろした人間関係もあったし、
「自分が観文研を支えている(つもり)なのに、何であれこれいわれるんだ!」
といった奢りや悔しさもあったが、今ではそれらはすべて消え去り、ただただきれいな思い出になっている。
そしてそこで得たもの、得られたものの大きさが今になってみるとよくわかる。
生涯唯一の師、民俗学者・宮本常一先生
「我に師なし 我に弟子なし」
そういいつづけてきた一匹狼のカソリだが、じつは1人、師がいる。それは柳田国男をしのぐとさえいわれている民俗学者の宮本常一先生だ。
宮本先生は生涯を通して4000日以上も旅された偉大な旅人。その足跡は日本国中に及ぶ。そんな宮本先生がつくられ、所長をされていた日本観光文化研究所に出入りするようになったのはスズキの250ccバイク、TC250を走らせ、2年あまりの「アフリカ一周」(1968年〜69年)から帰った直後のことで、当時カソリ、22歳。
その後、「世界一周」(1971年〜1972年)、「六大陸周遊」(1973年〜1974年)とたてつづけに世界を駆けめぐった。
 20歳の旅立ち。南部アフリカのモザンビークで。1968年4月から翌年12月までの「アフリカ一周」から帰ったあと、日本観光文化研究所に出入りするようになった。
20歳の旅立ち。南部アフリカのモザンビークで。1968年4月から翌年12月までの「アフリカ一周」から帰ったあと、日本観光文化研究所に出入りするようになった。 だが「六大陸周遊」の旅から帰ったときは、大きな壁にぶち当たってしまった。
それまでの、命を張って世界を駆けめぐってきたことがまるで無意味なことのように思え、何とも虚しい気分に襲われた。20代の大半を費やしてやってきたこが、一瞬の幻でも見たかのようにも思われた。
あれは一体、何だったのか…。
「もっと、もっと世界を駆けめぐりたい!」
という焼けつくような気持ちは萎え、旅への憧れも消えようとしていた。
このときカソリ、27歳。
我が旅人生、最大のピンチを救ってくれたのが日本観光文化研究所だった。
「よーし、今こそ、日本をまわろう!」
と心に決めたとき、うそのように気持ちが楽になった。
日本に目を向けたことによって、自分の体内にはまた新たな力が蘇ってきた。旅への意欲が湧き上がり、今度は無性に日本をまわりたくなったのだ。
世界から日本へ!
観文研にはより頻繁に出入りするようになり、宮本常一先生のお話を聞く機会が多くなった。観文研のあった東京・秋葉原から新宿までの電車の中でも、何度となく先生のお話を聞かせてもらった。
そんなこともあって観文研を足場にして日本をまわろうという気持ちが次第に強くなり、当時、観文研を取り仕切っていた先生のご子息の宮本千晴さんに頼み込んだ。
「先生と一緒に日本を歩かせて下さい!」
すると千晴さんは、
「なあ、カソリ、それだったら親父よりも神崎君と熊ちゃんの方がいい」
といって宮本先生の一番弟子といってもいい神崎宣武さん(現・旅の文化研究所所長)と熊ちゃんこと工藤員功さん(現・武蔵野美術大学民俗資料室)と一緒に日本を歩けるようにしてくれたのだ。
日本観光文化研究所はじつにユニークな組織で、宮本先生の教えに興味を持ったり、共感して「所員になりたい!」と思ったら、誰でも自由に所員になることができた。所員といっても、別に給料が出るわけでもなく、拘束されるわけでもなかったが…。
何ともありがたかったのは、
「君らを食わせてあげることはできないが、君らを歩かせてあげよう」
という宮本先生の方針どおり、所員は様々なテーマで日本中を旅する旅費をもらえたことだ。
あの頃のカソリは怖いものナシ。
「カソリさんは何で食ってるんですか?」
とよく聞かれたが、そのたびに平気な顔して、
「いやー、カスミを食ってますよ!」
といっていた。
そんな日本観光文化研究所(観文研)は1989年3月31日に解散。宮本常一先生はその8年前の1981年1月30日に亡くなられた…。