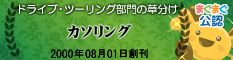アイヌ語地名(その2)
投稿日:2009年11月21日
イナウと稲穂と北の稲作
 国道5号の稲穂峠
国道5号の稲穂峠 北海道遺産の「アイヌ語地名」ということで、国道5号の稲穂峠を越えた。余市と倶知安の間の峠。「稲穂」はアイヌ語の「イナウ」(木の御幣)からきている。稲穂峠はほかにも木古内から上ノ国への道道5号、国縫から北檜山への国道230号にもある。また奥尻島の最北端の岬が稲穂岬。そこは聖地。「賽の河原園地」があり、積み重ねられた石塔が霊山的な雰囲気をかもし出している。
「イナウ」は木の御幣といったが、たとえばこのような使い方をする。
あるメノコ(女)が、夫が山猟に行った留守の間、朝夕の煮炊きを面倒がって、残り物ばかりを食べていた。するとある日、イロリ端の土間に横になって休んだところ、体が土にくっついて離れなくなった。
山猟から帰った夫は驚いて、急いで【イナウ】をつくり、アペ・フチ・カムイ(火の・おばあちゃんの・神様)に祈った。どうか妻を許してください。
おかげで、女は元通り起き上がることができた。
朝夕の煮炊きのためにイロリにくべる薪は、アペ・フチ・カムイの食物。その大事なものを女は差し上げなかった。それで罰をあたえられたのさ。
山猟から帰った夫は驚いて、急いで【イナウ】をつくり、アペ・フチ・カムイ(火の・おばあちゃんの・神様)に祈った。どうか妻を許してください。
おかげで、女は元通り起き上がることができた。
朝夕の煮炊きのためにイロリにくべる薪は、アペ・フチ・カムイの食物。その大事なものを女は差し上げなかった。それで罰をあたえられたのさ。
(アイヌの昔話より)
 旭川のアイヌ記念館のイナウ
旭川のアイヌ記念館のイナウそんな「イナウ」に「稲穂」の字を当てるところに、北海道人の稲に対する熱い想いが読み取れる。
 石狩平野の水田地帯
石狩平野の水田地帯北海道では亜熱帯作物の稲を道南から道北へと、どんどんと栽培エリアを拡大させ、亜寒帯でまで、稲をつくっている。そんな北海道での稲作を見たくって、20余年ほど前、列車で函館から稚内まで行った。
1986年9月16日、函館発8時02分の特急「北斗3号」に乗った。列車をのりつぎ稚内まで行くのだが、一番の目的は車窓から稲を見ることだった。
札幌行きの「北斗3号」は函館の市街地を抜け出ると、広々とした草原を走る。木の柵で囲まれた牧場で馬が草を食む風景は、いかにも北海道らしいものだった。それとともに、金色に染まった稲田の風景も見たが、それは北海道が日本であることをあらためて感じさせてくれた。
函館平野(大野平野)は北海道の稲作発祥の地。旧大野町の文月で元禄年間(1688年~1704年)に水稲栽培がおこなわれた記録が残っている。しかし北海道で稲作が本格的におこなわれるようになるのは明治になってからのこと。稲作地帯は短期間に石狩、空知、上川と北に延びていく。
「函館→稚内」の車窓から、日本人がどこまで米をつくっているのか、それを見極めようと心に決めて北海道に乗り込んできたのだ。
列車はスギやカラマツの植林されている山地にさしかかり、峠のトンネルを抜け出ると、車窓にはすばらしい風景が展開される。真っ青な湖の向こうに火山が聳えてる。駒ヶ岳だ。湖は抜けるような青空を映し、湖面の青さが増幅されていた。
8時44分、森着。森を過ぎると、列車は内浦湾に沿って走る。右側の車窓からは海が見え、海沿いには漁村が点在している。浜はどこもコンブ漁でにぎわいをみせ、誰もが忙しげにコンブを干している。左側の車窓からは牧場が見えている。サイロが見える。肉牛、乳牛、馬と家畜の種類が多彩だ。
9時31分、長万部着。ここは函館本線と室蘭本線の分岐駅。「北斗3号」は室蘭本線経由で札幌に向かう。
長万部を過ぎると、海岸には地を這うほどの、背の低いカシワやマツの木が、強い潮風に吹かれて揺れている。やがて前方には大山塊が迫ってくる。列車はトンネルに突入。全長2726メートルの礼文華トンネル。抜け出たあともトンネルが連続した。大山塊が内浦湾に落ち込むこのあたりは、北海道版の親不知、子不知といったところだ。
10時01分、洞爺着。左手には爆発の跡も生々しい有珠山が見える。吹き飛んだ山頂周辺に草木はまったく見られず、焼けただれた山肌がむき出しになっている。
列車が長流川にかかる鉄橋にさしかかると、有珠山の裾野越しには昭和新山が見えてくる。豊満な乳房のような盛り上りを見せる昭和新山。鉄橋を渡ると、広々とした稲田の中を走る。その向こうに見える有珠山、昭和新山という大小2つの活火山は異形を呈していた。
10時31分、東室蘭着。室蘭は製鉄の町。新日本製鉄の室蘭製鉄所を間近に見る。東室蘭→札幌→旭川間は北海道鉄道網の中心で、電化区間となり、特急「ライラック」が1日に何本も走っている。
11時14分、苫小牧着。苫小牧は製紙の町。ここには王子製紙の工場がある。
苫小牧を過ぎると、海岸から内陸に入っていく。車窓には勇払平野が広がる。「原野」がぴったりするような勇払平野。アフリカのサバンナ地帯を連想させる乾いた草原の中に、灌木が点在している。
空港のある千歳あたりが太平洋側の勇払平野と、日本海側の石狩平野の分水界になっているが、どのあたりがそうなのかわからないまま、列車は石狩平野に入っていった。それとともに原野は豊かな農地に変り、大型のハーベスターがジャガイモを収穫していた。
こうして特急「北斗3号」は札幌の市街地に入り、12時05分、札幌駅に到着。駅周辺の北海道庁旧本庁舎や時計台を見てまわり、大通り公園、中島公園を歩き、ひと晩、札幌に泊まった。
翌朝、7時00分発の網走行き特急「オホーツク」に乗り込み、旭川に向かう。車内はほぼ満員。サラリーマン然とした乗客が多い。札幌から旭川への出張といった感じだ。豊平川の鉄橋を渡り、札幌の市街地を抜け、列車は石狩平野を走る。
トウモロコシ畑やジャガイモ、タマネギ、ダイズの畑が見える。牧草地も見える。だがそれら畑作地や牧草地よりも、一面に黄金色に染まった稲田の方が、はるかに広い面積を占めている。また、1枚の稲田は内地とは比べものにならないくらいに広い。
石狩平野で稲作が本格的にはじまったのは、明治28年に北海道庁が稲作試験場を設けてからのことだという。「坊主」という優れた耐寒品種が生まれ、内地とは違う直播の稲作技術が発達した。いかにも大規模農業の北海道らしい話だ。
明治30年には北海道拓殖銀行が設立され、農民に資金を貸し出すようになってからというもの、泥炭地の土地改良ができるようになった。そのため低地で水の得やすいところはことごとく水田化され、石狩平野は北海道の大穀倉地帯になった。
7時32分、岩見沢着。岩見沢を過ぎると、右手には夕張山地へとつづくなだらかな山々が見えてくる。美唄、砂川と通る。炭鉱の相次ぐ閉山で、これらの町々は活気をなくし、駅舎にも寂しげな影が漂っている。雑草のはえた構内の線路がもの悲しい。
8時04分、滝川着。ここは根室本線との分岐駅。滝川を出るとまもなく石狩川を渡る。石狩平野につづいての空知平野は、車窓から見る限りでは、新潟平野や富山平野のように稲作一辺倒。広大な水田地帯がつづく。
8時22分、深川着。ここは留萌本線との分岐駅。深川を過ぎると石狩川の両側には山々が迫り、川岸には安山岩の奇岩、巨岩が次々に現れる。神居古タンだ。列車はトンネルを抜け出ると、上川盆地に入っていった。
8時45分、旭川着。ここは石北本線と宗谷本線の分岐駅。特急「オホーツク」の乗客の大半は旭川で降りたが、列車はさらに網走まで行く。
ここで8時52分発の急行「礼文」に乗り換える。「旭川→稚内」間には「礼文」、「天北」、「宗谷」、「利尻」と、1日4本の急行が走っているが、特急はない。
2両編成の急行「礼文」は定刻通りに旭川駅を発車し、上川盆地を走る。
石狩平野、空知平野と同じような稲作地帯の上川盆地だが、
「これが平野と盆地の違いかな」
と思わせたのは、1枚1枚の稲田が狭くなったこと。
上川盆地で稲作が本格化したのは、石狩平野よりも10年あまり遅れた明治30年代後半のこと。冬は気温が氷点下20度以下に下がる酷寒の地だが、夏は気温が30度を超える盆地特有の気候が稲作を可能にした。
列車は上川盆地の北端にさしかかり、ジーゼルのうなりを上げながら、塩狩峠を登っていく。目をこらして稲田をみつづける。峠下の最後の稲田が消えたとき、
「あー、これで日本の稲作地帯が終った!」
と、思った。
塩狩峠に近づくにつれて、山々を覆う樹木は広葉樹から針葉樹に変り、葉の緑の濃いトドマツとそれよりは緑の薄いエゾマツが目だってくる。石狩川と天塩川という北海道の2大河川の分水嶺になっている塩狩峠には塩狩駅があり、駅前には温泉宿があった。
列車は峠を下る。天塩川流域の名寄盆地まで下って驚かされたのは、上川盆地で消えたとばかり思っていた稲田がまた車窓に現れてきたことだ。その驚きは、日本の稲作の北限が「ここまで延びてきているのか!」という感動でもあった。
9時28分、士別着。まだ稲田が見える。
10時01分、名寄着。まだ稲田が見える。
列車は名寄を出ると、天塩川の右岸を走るようになる。蛇行を繰り返す天塩川。名寄盆地はその幅をぐっとせばめ、やがて列車は谷間に入る。そこで稲田は消えた。
10時22分、美深着。消えたとばかり思った稲田が、なんとまた、姿を現したのだ。いったい日本人は、どこまで北で稲をつくっているのか。しかし、さすがにこのあたりまで来ると、稲田があるとはいっても、ダイズやトウモロコシ、ジャガイモなどの畑や牧草地の方がはるかに広い面積を占めている。
美深を出て2つ目の駅、紋穂内駅の手前で稲田を見た。それが車窓から見た最後の稲田になった。紋穂内は地図で見ると、北緯44度30分前後であろうか。
稲田が見えなくなると、車窓を流れていく風景は急速に荒涼感を増してくる。
それとともに何ともいえない寂しさを感じた。疎外感とでもいおうか、別な世界に1人、放り出されたような寂しさだった。
この寂しさはどこから来るのか…。
稲田を見慣れ、米を食べつづけてきた日本人としての血が、そう感じさせるのか。
10時57分、音威子府着。音威子府を過ぎると、天塩川の両岸には牧場がつづく。乳牛の牧場が主だが、羊の牧場も見える。列車が北上するにつれて牧場の規模は大きくなり、より機械化されてくる。大型機械で刈り取られた牧草が、ロール状に巻かれている。そんな干草を満載にしたトラックが走り去っていく。
12時03分、幌延着。このあたりまで来ると、車窓に広がる風景は日本離れした雄大なものになり、地平線が見える。列車はサロベツ原野の東端を走っている。日本海からの北西の強風が吹きつけるからなのだろう、線路沿いの樹木は南東に向かっておじぎするように傾いている。
平原地帯から丘陵地帯に入っていく。丘陵の斜面はクマザサで覆いつくされている。クマザサの風に哭く音が聞こえてくるようだった。
日本海が見えてきた。
列車は海岸段丘の上を走っているので、長く延びる海岸線を見下ろした。日本海の向こうに礼文島と利尻島が見える。利尻島の利尻富士が抜けるような青空に、つんと尖った山頂を向けている。
すばらしい眺めを乗客に見てもらおうというはからいなのだろう、列車はスピードを落とし、「正面に見えるのが利尻富士です」の車内アナウンスがあった。
こうして13時05分、急行「礼文」は終着の稚内駅に到着した。
札幌行きの「北斗3号」は函館の市街地を抜け出ると、広々とした草原を走る。木の柵で囲まれた牧場で馬が草を食む風景は、いかにも北海道らしいものだった。それとともに、金色に染まった稲田の風景も見たが、それは北海道が日本であることをあらためて感じさせてくれた。
函館平野(大野平野)は北海道の稲作発祥の地。旧大野町の文月で元禄年間(1688年~1704年)に水稲栽培がおこなわれた記録が残っている。しかし北海道で稲作が本格的におこなわれるようになるのは明治になってからのこと。稲作地帯は短期間に石狩、空知、上川と北に延びていく。
「函館→稚内」の車窓から、日本人がどこまで米をつくっているのか、それを見極めようと心に決めて北海道に乗り込んできたのだ。
列車はスギやカラマツの植林されている山地にさしかかり、峠のトンネルを抜け出ると、車窓にはすばらしい風景が展開される。真っ青な湖の向こうに火山が聳えてる。駒ヶ岳だ。湖は抜けるような青空を映し、湖面の青さが増幅されていた。
8時44分、森着。森を過ぎると、列車は内浦湾に沿って走る。右側の車窓からは海が見え、海沿いには漁村が点在している。浜はどこもコンブ漁でにぎわいをみせ、誰もが忙しげにコンブを干している。左側の車窓からは牧場が見えている。サイロが見える。肉牛、乳牛、馬と家畜の種類が多彩だ。
9時31分、長万部着。ここは函館本線と室蘭本線の分岐駅。「北斗3号」は室蘭本線経由で札幌に向かう。
長万部を過ぎると、海岸には地を這うほどの、背の低いカシワやマツの木が、強い潮風に吹かれて揺れている。やがて前方には大山塊が迫ってくる。列車はトンネルに突入。全長2726メートルの礼文華トンネル。抜け出たあともトンネルが連続した。大山塊が内浦湾に落ち込むこのあたりは、北海道版の親不知、子不知といったところだ。
10時01分、洞爺着。左手には爆発の跡も生々しい有珠山が見える。吹き飛んだ山頂周辺に草木はまったく見られず、焼けただれた山肌がむき出しになっている。
列車が長流川にかかる鉄橋にさしかかると、有珠山の裾野越しには昭和新山が見えてくる。豊満な乳房のような盛り上りを見せる昭和新山。鉄橋を渡ると、広々とした稲田の中を走る。その向こうに見える有珠山、昭和新山という大小2つの活火山は異形を呈していた。
10時31分、東室蘭着。室蘭は製鉄の町。新日本製鉄の室蘭製鉄所を間近に見る。東室蘭→札幌→旭川間は北海道鉄道網の中心で、電化区間となり、特急「ライラック」が1日に何本も走っている。
11時14分、苫小牧着。苫小牧は製紙の町。ここには王子製紙の工場がある。
苫小牧を過ぎると、海岸から内陸に入っていく。車窓には勇払平野が広がる。「原野」がぴったりするような勇払平野。アフリカのサバンナ地帯を連想させる乾いた草原の中に、灌木が点在している。
空港のある千歳あたりが太平洋側の勇払平野と、日本海側の石狩平野の分水界になっているが、どのあたりがそうなのかわからないまま、列車は石狩平野に入っていった。それとともに原野は豊かな農地に変り、大型のハーベスターがジャガイモを収穫していた。
こうして特急「北斗3号」は札幌の市街地に入り、12時05分、札幌駅に到着。駅周辺の北海道庁旧本庁舎や時計台を見てまわり、大通り公園、中島公園を歩き、ひと晩、札幌に泊まった。
翌朝、7時00分発の網走行き特急「オホーツク」に乗り込み、旭川に向かう。車内はほぼ満員。サラリーマン然とした乗客が多い。札幌から旭川への出張といった感じだ。豊平川の鉄橋を渡り、札幌の市街地を抜け、列車は石狩平野を走る。
トウモロコシ畑やジャガイモ、タマネギ、ダイズの畑が見える。牧草地も見える。だがそれら畑作地や牧草地よりも、一面に黄金色に染まった稲田の方が、はるかに広い面積を占めている。また、1枚の稲田は内地とは比べものにならないくらいに広い。
石狩平野で稲作が本格的にはじまったのは、明治28年に北海道庁が稲作試験場を設けてからのことだという。「坊主」という優れた耐寒品種が生まれ、内地とは違う直播の稲作技術が発達した。いかにも大規模農業の北海道らしい話だ。
明治30年には北海道拓殖銀行が設立され、農民に資金を貸し出すようになってからというもの、泥炭地の土地改良ができるようになった。そのため低地で水の得やすいところはことごとく水田化され、石狩平野は北海道の大穀倉地帯になった。
7時32分、岩見沢着。岩見沢を過ぎると、右手には夕張山地へとつづくなだらかな山々が見えてくる。美唄、砂川と通る。炭鉱の相次ぐ閉山で、これらの町々は活気をなくし、駅舎にも寂しげな影が漂っている。雑草のはえた構内の線路がもの悲しい。
8時04分、滝川着。ここは根室本線との分岐駅。滝川を出るとまもなく石狩川を渡る。石狩平野につづいての空知平野は、車窓から見る限りでは、新潟平野や富山平野のように稲作一辺倒。広大な水田地帯がつづく。
8時22分、深川着。ここは留萌本線との分岐駅。深川を過ぎると石狩川の両側には山々が迫り、川岸には安山岩の奇岩、巨岩が次々に現れる。神居古タンだ。列車はトンネルを抜け出ると、上川盆地に入っていった。
8時45分、旭川着。ここは石北本線と宗谷本線の分岐駅。特急「オホーツク」の乗客の大半は旭川で降りたが、列車はさらに網走まで行く。
ここで8時52分発の急行「礼文」に乗り換える。「旭川→稚内」間には「礼文」、「天北」、「宗谷」、「利尻」と、1日4本の急行が走っているが、特急はない。
2両編成の急行「礼文」は定刻通りに旭川駅を発車し、上川盆地を走る。
石狩平野、空知平野と同じような稲作地帯の上川盆地だが、
「これが平野と盆地の違いかな」
と思わせたのは、1枚1枚の稲田が狭くなったこと。
上川盆地で稲作が本格化したのは、石狩平野よりも10年あまり遅れた明治30年代後半のこと。冬は気温が氷点下20度以下に下がる酷寒の地だが、夏は気温が30度を超える盆地特有の気候が稲作を可能にした。
列車は上川盆地の北端にさしかかり、ジーゼルのうなりを上げながら、塩狩峠を登っていく。目をこらして稲田をみつづける。峠下の最後の稲田が消えたとき、
「あー、これで日本の稲作地帯が終った!」
と、思った。
塩狩峠に近づくにつれて、山々を覆う樹木は広葉樹から針葉樹に変り、葉の緑の濃いトドマツとそれよりは緑の薄いエゾマツが目だってくる。石狩川と天塩川という北海道の2大河川の分水嶺になっている塩狩峠には塩狩駅があり、駅前には温泉宿があった。
列車は峠を下る。天塩川流域の名寄盆地まで下って驚かされたのは、上川盆地で消えたとばかり思っていた稲田がまた車窓に現れてきたことだ。その驚きは、日本の稲作の北限が「ここまで延びてきているのか!」という感動でもあった。
9時28分、士別着。まだ稲田が見える。
10時01分、名寄着。まだ稲田が見える。
列車は名寄を出ると、天塩川の右岸を走るようになる。蛇行を繰り返す天塩川。名寄盆地はその幅をぐっとせばめ、やがて列車は谷間に入る。そこで稲田は消えた。
10時22分、美深着。消えたとばかり思った稲田が、なんとまた、姿を現したのだ。いったい日本人は、どこまで北で稲をつくっているのか。しかし、さすがにこのあたりまで来ると、稲田があるとはいっても、ダイズやトウモロコシ、ジャガイモなどの畑や牧草地の方がはるかに広い面積を占めている。
美深を出て2つ目の駅、紋穂内駅の手前で稲田を見た。それが車窓から見た最後の稲田になった。紋穂内は地図で見ると、北緯44度30分前後であろうか。
稲田が見えなくなると、車窓を流れていく風景は急速に荒涼感を増してくる。
それとともに何ともいえない寂しさを感じた。疎外感とでもいおうか、別な世界に1人、放り出されたような寂しさだった。
この寂しさはどこから来るのか…。
稲田を見慣れ、米を食べつづけてきた日本人としての血が、そう感じさせるのか。
10時57分、音威子府着。音威子府を過ぎると、天塩川の両岸には牧場がつづく。乳牛の牧場が主だが、羊の牧場も見える。列車が北上するにつれて牧場の規模は大きくなり、より機械化されてくる。大型機械で刈り取られた牧草が、ロール状に巻かれている。そんな干草を満載にしたトラックが走り去っていく。
12時03分、幌延着。このあたりまで来ると、車窓に広がる風景は日本離れした雄大なものになり、地平線が見える。列車はサロベツ原野の東端を走っている。日本海からの北西の強風が吹きつけるからなのだろう、線路沿いの樹木は南東に向かっておじぎするように傾いている。
平原地帯から丘陵地帯に入っていく。丘陵の斜面はクマザサで覆いつくされている。クマザサの風に哭く音が聞こえてくるようだった。
日本海が見えてきた。
列車は海岸段丘の上を走っているので、長く延びる海岸線を見下ろした。日本海の向こうに礼文島と利尻島が見える。利尻島の利尻富士が抜けるような青空に、つんと尖った山頂を向けている。
すばらしい眺めを乗客に見てもらおうというはからいなのだろう、列車はスピードを落とし、「正面に見えるのが利尻富士です」の車内アナウンスがあった。
こうして13時05分、急行「礼文」は終着の稚内駅に到着した。
『あるく みる きく』第240号より
※あるく みる きく:カソリが師と仰ぐ、日本を代表する民俗学者・宮本常一が主宰した日本観光文化研究所から発行された旅雑誌。1967(昭和42)年から1988(昭和63)年まで発行された。
Category: 北海道遺産コラム